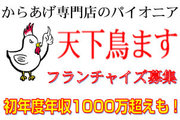テイクアウト専門店を始めたい!許可は必要?開業の流れを解説

テイクアウト専門店を始めてみたいけど、何か特別な許可って必要なのかな・・・?
テイクアウト専門店の開業を検討する際、多くの人が最初に疑問に思うのが許可の要否です。
飲食店を運営するには、
食品衛生法をはじめとする法律に基づいた手続きが不可欠であり、これはテイクアウト専門店も例外ではありません。
この記事では、テイクアウト販売に必要な許可の種類や、具体的な開業までの流れ、
そして安全な商品提供に欠かせない衛生管理の注意点について、網羅的に解説します。
1
飲食店がテイクアウトを始めるのに許可はいる?いらない?
コロナ禍以降、持ち帰り需要の増加に伴い、多くの飲食店がテイクアウト販売を導入しました。
既存の飲食店が新たにテイクアウトを始める場合、
追加の営業許可は基本的に不要なケースが多いですが、販売する商品や形態によっては新たな許可が求められることもあります。
店内飲食を提供する「飲食店営業」の許可範囲を正しく理解し、自身の営業形態がどのケースに該当するのかを確認することが重要です。
店内で調理した料理なら原則として追加の許可は不要
すでに「飲食店営業許可」を取得している店舗であれば、
その許可を受けた厨房施設内で調理した料理をテイクアウト商品として販売する場合、原則として新たな許可を取得する必要はありません。
飲食店営業許可は、施設内で調理した飲食物を客に提供する営業全般を対象としており、その提供方法が店内飲食か持ち帰りかを問わないためです。
したがって、普段お店で提供しているカレーやパスタといった一般的な料理を弁当として販売するだけであれば、既存の許可の範囲内で対応が可能です。
ただし、調理や販売に関する衛生管理の基準は、店内飲食と同様に遵守しなくてはなりません。
2
《要注意!》テイクアウトで新たな営業許可が必要になる4つのケース
テイクアウト販売は、基本的に飲食店営業許可の範囲内で行えますが、
特定の食品を扱ったり、通常とは異なる方法で販売したりする場合には、追加で営業許可や免許の取得が義務付けられます。
これらのルールを知らずに営業すると、法律違反となる可能性があるため注意が必要です。
ここでは、テイクアウトで新たな許可が必要になる代表的な4つのケースと、
それぞれの注意点について具体的に説明します。
ケース1:テイクアウト専門店を新規でオープンする場合
新たにテイクアウト専門店を開業する場合は、
店舗を管轄する保健所から「飲食店営業許可」を取得することが必須です。
この許可を得るためには、店舗の施設が保健所の定める基準を満たしている必要があり、例えばシンクの数や給湯設備の設置、冷蔵設備の性能などが細かく定められています。
また、施設ごとに食品衛生責任者を1名置くことも義務付けられています。
物件を探す段階であれば、どのような改装が必要になるか、事前に保健所に相談しておくとスムーズに手続きを進められます。
専門店として特定のメニューに絞る場合でも、この許可は必ず取得しなくてはなりません。
ケース2:菓子やアイスクリームなど特定の食品を製造・販売する場合
テイクアウトで販売する商品によっては、飲食店営業許可とは別に専門の製造業許可が必要になります。
例えば、
店舗でパンやケーキ、クッキーなどの菓子を製造して販売するには
「菓子製造業許可」が求められます。
同様に、
自家製アイスクリームやシャーベットを製造・販売するためには
「アイスクリーム類製造業許可」が必要です。
これらは飲食店営業許可とは異なる施設基準が定められているため、注意しなくてはなりません。
ランチセットのフードメニューに自家製のケーキを3種付けるといった場合でも、
製造場所や設備によってはこの許可の対象となる可能性があります。
ケース3:お弁当と一緒にお酒を販売する場合
調理した料理や弁当と一緒にお酒をテイクアウトで販売するには、
保健所が管轄する飲食店営業許可とは別に、
税務署が管轄する「酒類小売業免許」を取得する必要があります。
具体的には、容器入りの酒類を継続的に販売するための「一般酒類小売業免許」が該当します。
過去には新型コロナウイルス対策の特例として「料飲店等期限付酒類小売業免許」が設けられていましたが、
制度が変更されている可能性もあるため、最新の情報を必ず税務署に確認してください。
お酒の販売を検討している場合は、免許取得までに時間がかかることも考慮し、早めに準備を始めることが重要です。
ケース4:店舗とは別の施設で調理して販売する場合
営業許可は、調理を行う施設ごとに取得する必要があります。
そのため、許可を得ている店舗の厨房とは別の場所で調理したものを販売する場合、その調理施設についても新たに営業許可を取得しなければなりません。
例えば、複数の店舗で販売する商品を一括して調理するセントラルキッチンを設けるケースなどがこれに該当します。
イベント会場での臨時出店や、許可のない自宅のキッチンなどで調理したものを販売することは認められていません。
必ず、営業許可を取得した施設内で調理を行うルールを遵守し、安全な商品を提供する体制を整えることが求められます。
3
テイクアウト専門店の開業に向けた5つのステップ
テイクアウト専門店の開業は、しっかりとした計画と準備が成功の鍵を握ります。
1人で開業する場合であっても、物件の選定からメニュー開発、各種申請、告知活動まで、やるべきことは多岐にわたります。
特に初期投資に占める物件取得費や内装工事費の割合は大きいため、事業計画の段階で慎重な検討が求められます。
ここでは、開業までの道のりを具体的な5つのステップに分けて解説します。
ステップ1:計画段階で保健所に事前相談する
事業計画や店舗のコンセプト、メニューがある程度固まり、物件の候補が決まったら、内装工事を始める前に管轄の保健所へ事前相談に行きましょう。
店舗の図面などを持参して、予定している営業形態でどのような許可が必要になるか、また、施設が構造上の基準を満たしているかを確認してもらいます。
この段階で相談することで、工事完了後に基準を満たしていないことが発覚し、追加の工事が必要になるといった事態を防げます。
保健所への相談は予約制の場合が多いため、事前に電話で連絡を入れてから訪問するようにしてください。
ステップ2:必要な書類を揃えて営業許可を申請する
保健所との事前相談を終え、店舗の工事が完了する見込みが立ったら、営業許可の申請手続きに進みます。
一般的に必要となるのは、下記です。
- 営業許可申請書
- 店舗の営業設備の大要・配置図
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査成績書(貯水槽使用水や井戸水の場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類
申請から許可証の交付までには、施設検査などを含めて10営業日以上かかることもあります。
オープン日から逆算し、余裕を持ったスケジュールで申請手続きを行うことが大切です。
ステップ3:持ち帰りに適したメニューを開発する
テイクアウト販売では、
顧客が購入してから食べるまでに時間が経過することを考慮したメニュー開発が不可欠です。
・冷めても美味しく食べられる
・汁漏れしにくい
・時間が経っても食感が損なわれにくい
といった工夫が求められます。
既存のレストランの人気メニューをそのまま提供するのではなく、
テイクアウト用に味付けや調理法をアレンジすることも有効です。
また、見た目の魅力も重要であり、容器に盛り付けた際の彩りや見栄えも考慮することで、顧客満足度を高められます。
おすすめの食材や調理法を研究し、独自の人気メニューを開発してください。
ステップ4:容器や備品など必要なものを準備する
メニューが決まったら、料理に合ったテイクアウト用の容器やカトラリー、箸、袋などの備品を準備します。
容器は、料理の温度を保つ保温性や、持ち運びやすさ、汁漏れしにくい密閉性などを考慮して選びましょう。
また、ブランドイメージを伝えるために、店名やロゴの入ったオリジナル容器を作成するのも効果的です。
最近では環境に配慮した素材の容器も増えており、店のコンセプトに合わせて選択肢を広げられます。
これらの備品は、包装資材の専門店やネット通販などでまとめて購入すると効率的です。
ステップ5:SNSやチラシでテイクアウト開始を告知する
テイクアウト販売を始めたことを広く知ってもらうための告知活動も重要です。
InstagramやX(旧Twitter)などのSNSを活用し、魅力的な料理の写真を投稿してメニュー情報を発信するのは効果的な手法です。
店舗の前に看板やのぼりを設置したり、近隣の家庭やオフィスにチラシをポスティングしたりするのも有効でしょう。
また、デリバリーサービスと連携することで、配達エリアの顧客にアプローチすることも可能です。
どのような顧客にメッセージを届けたいかを考え、複数の方法を組み合わせて告知を行ってください。
4
食中毒を防ぐ!テイクアウト販売で必ず守るべき注意点
テイクアウト商品は、店内飲食と比べて調理から喫食までの時間が長くなるため、食中毒のリスクが高まります。
安全な商品を提供し、顧客の信頼を得るためには、徹底した衛生管理が不可欠です。
調理過程だけでなく、適切なメニュー選定や、アレルギー情報などの食品表示も重要な要素となります。
万が一の事故を防ぐため、事業者は衛生管理に関する正しい知識を身につけ、日々の営業で実践しなくてはなりません。
調理から提供までの徹底した衛生管理を心がける
テイクアウト販売における衛生管理は、店内飲食以上に厳格に行う必要があります。
調理前の手洗いやアルコール消毒、調理器具の洗浄・殺菌を徹底することはもちろん、食材は中心部まで十分に加熱し、調理後は速やかに冷却して食中毒菌の増殖を防ぎます。
特に、盛り付けは菌が付着しないよう、使い捨ての手袋を着用して清潔な環境で行うことが重要です。
大手レストランやチェーン店が実践しているような衛生管理マニュアルを作成し、スタッフ全員が同じ意識で作業に取り組む体制を構築してください。
生ものや火の通りが不十分なメニューの提供は避ける
食中毒のリスクを最小限に抑えるため、テイクアウトでは生ものや加熱が不十分なメニューの提供は極力避けるべきです。
刺身や生の魚介類を使ったすし、半生の肉を使ったローストビーフやステーキなどは、温度管理が難しく、菌が繁殖しやすいため持ち帰りには適していません。
特に気温と湿度が高くなる夏場は、より一層の注意が求められます。
どうしても提供したい場合は、保冷剤を添付し、
「すぐに食べてください」
といった注意喚起を口頭と書面の両方で行うなど、リスクを顧客に明確に伝える対策が必須です。
消費期限やアレルギーなど必要な情報をラベルに記載する
テイクアウト商品には、顧客が安全に食べられるように必要な情報を明記したラベルを貼付することが推奨されます。
・商品名、
・消費期限(または賞味期限)
・保存方法(例:要冷蔵10℃以下)
・アレルギー物質の表示
・製造者の名称と連絡先
などを記載します。
これにより、顧客は安心して商品を購入できるだけでなく、食物アレルギーを持つ人が誤って食べてしまう事故を防ぐことにもつながります。
たとえ500円のお弁当であっても、
これらの表示は食の安全を守る上で非常に重要であり、トラブル防止の観点からも必ず実施してください。
クーポンなどの販促情報とは別に、必要な情報をしっかりと伝えましょう。
5
まとめ
テイクアウト営業を始めるためには、
基本的な「飲食店営業許可」の取得に加え、販売する商品や形態に応じて追加の許可や免許が必要になる場合があります。
テイクアウトの需要は多様化しており、利用者は駅の近くや夜に利用できる店、そばやチェーン店など、様々な条件で近くの飲食店一覧を探します。
どのような形態で営業するにしても、まずは管轄の保健所に相談し、法律やルールを遵守することが事業成功の第一歩です。
開業に向けた計画的な準備と、徹底した衛生管理を実践してください。
オススメの商材・サービスを集めてみました!
-

ピザハット
-

高級とんかつ専門店「とんかつ慶」
-

すしと酒-箔-
-
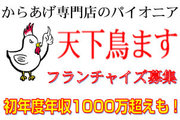
からあげ専門店「天下鳥ます」
-

【赤字保証付き】完全代行型飲食店フランチャイズamau
-

大石久右衛門
-

カレー専門店「日乃屋カレー」
-

個別指導WAM(ワム)
-

創業54年の安定基盤がある焼肉店「安楽亭」
-

らあめん花月嵐
-

ビカンテック加盟店募集
-

OWL福祉事業「障がい者グループホーム」
まずは資料請求してみませんか?もちろん無料です。
(簡単な会員登録が必要です)
資料請求してみる





 0120-536-015
0120-536-015