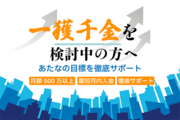個人事業主で従業員5人以下を雇うときの社会保険はどうする?加入義務や手続きも解説
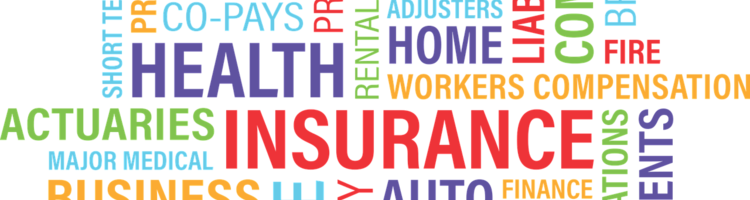
個人事業主が従業員を雇用する際、社会保険制度への理解は欠かせません。
従業員数によって加入義務の有無が変わり、特に5人以下の場合は任意適用となることがあります。
また、社会保険には健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の4種類があり、それぞれ加入条件が異なります。
労働保険である雇用保険と労災保険は、従業員を1人でも雇用すれば加入義務があるため注意が必要です。
1
個人事業主の社会保険の基本情報
個人事業主にとって、
社会保険の仕組みは複雑に感じられるかもしれませんが、その基本を理解することは、従業員の福利厚生や事業運営において非常に重要です。
社会保険には、従業員の生活を支える健康保険、厚生年金保険、介護保険、そして労働災害保険や雇用保険といった労働保険が含まれており、それぞれ加入条件が異なります。
事業主自身の社会保険は、通常、国民健康保険と国民年金が基本となりますが、従業員を雇用する場合には、その人数や事業形態によって、厚生年金などへの加入を検討する選択肢も出てきます。
2
社会保険の種類と加入条件
社会保険には、病気やけが、老後の生活、失業時などに備えるための保険が含まれています。
主な種類として、
健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つがあり、
それぞれ加入条件が異なります。
以下にそれぞれの概要や加入条件を分かりやすくまとめました。
1.健康保険
病気やけが、出産、死亡時の医療費補助や給付が受けられる保険です。
会社員や公務員は、原則として雇用先を通じて「健康保険(協会けんぽや健康保険組合)」に加入します。
一般的には、週30時間以上働く正社員や、週20時間以上働き、かつ収入が一定以上のパートタイマーも加入対象です。
2.厚生年金保険
老後や障害の際、または遺族への年金給付を行う保険です。
会社員や公務員は、健康保険と同様に雇用先を通じて厚生年金に加入します。
一定の条件を満たすパートタイマー(週20時間以上の勤務、月額収入8.8万円以上、1年以上の勤務見込み、従業員数が101人以上の企業に勤務)も加入対象です。
自営業者やフリーランスは国民年金に加入します。
3.介護保険
高齢者や要介護者が介護サービスを利用できる保険です。
健康保険に加入している40歳以上の人が自動的に加入します。
40歳から64歳までの人は、特定の疾病(16の特定疾患)の場合のみ介護サービスが受けられます。。
65歳以上になると、要支援・要介護認定を受ければサービスを利用可能です。
4.雇用保険
失業時や育児・介護休業時に給付を受けられる保険です。
週20時間以上働く労働者で、31日以上引き続き雇用される見込みがある場合に加入します。
アルバイトやパートタイマーでも、勤務時間が週20時間以上であれば対象です。
5.労災保険(労働者災害補償保険)
業務中や通勤途中の事故や災害に対して医療給付や補償を受けられる保険です。
すべての労働者が対象で、勤務形態や勤務時間に関係なく適用されます。
事業者が全額負担し、パートやアルバイト、派遣社員なども含めて労働者が加入対象です。
労働者の生活保障やリスクに備えるためのもので、多くは雇用先を通じて加入手続きが行われます。
3
従業員5人以上を雇う場合の加入義務
従業員を5人以上雇用する場合、社会保険への加入が義務付けられます。
具体的には、健康保険、介護保険、厚生年金保険への加入が必要です。
これは「強制適用事業所」と呼ばれ、
業種を問わず、社会保険への加入が義務となります。
例えば、事務処理を主とする事務所や、製造業、建設業などの事業は、従業員が5人以上になると強制適用事業所となります。
ただし、例外として、個人経営の農林漁業や、旅館・料理飲食業など、特定のサービス業に分類される事業所は、従業員が5人以上であっても「任意適用事業所」となり、加入は任意とされています。
この「任意適用事業所」に該当する事業主が社会保険に加入する場合は、
事業主が希望し、従業員の過半数の同意を得て年金事務所に申請することで、社会保険に加入できます。
加入義務がある場合、事業主は保険料の半額を負担する義務が生じ、従業員も給与から保険料が天引きされます。
社会保険への加入は、従業員にとって医療費の自己負担割合の軽減や、老後の年金受給額の増加など、多くのメリットがあります。
また、事業主にとっても、従業員の定着率向上や優秀な人材の確保につながるというメリットが期待できます。
4
従業員5人未満を雇う場合の任意適用
従業員が5人未満の場合、社会保険への加入は原則任意となります。
この場合、健康保険や厚生年金に加入するかどうかは事業主の判断となりますが、加入するとさまざまな利点があります。
- 【健康保険と厚生年金保険の任意適用】
- 概要:
法人の場合、従業員数にかかわらず、健康保険と厚生年金の加入が義務ですが、個人事業所で従業員が5人未満の事業所については、原則として加入義務はありません。
ただし、事業主が希望すれば任意で適用を受けることが可能です。 - 加入条件:
従業員5人未満の事業所であっても、事業主が従業員と協議のうえで社会保険への加入を希望する場合、管轄の年金事務所で「任意適用」の申請ができます。
事業所内の労働者の過半数の同意が必要です(過半数を代表する者が同意する形でも可)。
年金事務所による審査を経て承認されれば、従業員全員が健康保険と厚生年金に加入することになります。
メリット
従業員が健康保険や厚生年金の保障を受けられるため、企業としての福利厚生が充実します。
従業員の老後保障が充実するため、従業員の満足度や企業への信頼が向上し、離職防止や人材確保に役立つことがあります。
デメリット
事業主負担の保険料が発生するため、コスト面での負担が増える可能性があります。
個人事業主であっても、社会保険の保障を手厚くすることで従業員の生活の安定と満足度向上につながるため、任意適用を検討する事業所もあります。
5
雇用保険・労災保険への加入は義務
個人事業主は、雇用保険や労災保険への加入が義務付けられています。
特に、労災保険は職場での事故や病気に対する保障を提供するもので、従業員を1人でも雇ったら加入が必須です。
雇用保険についても、一定の条件を満たす場合には加入することが求められます。たとえば、31日以上雇用する見込みがあり、週20時間以上勤務する場合には、雇用保険への加入が必要です。
これにより、従業員が失業した際の保障を受けられ、社会的なリスクに備えることができるでしょう。個人事業主としては、こうした保険への加入を通じて、従業員に対する責任を果たすことが重要です。
6
個人事業主の社会保険に関する手続き
以下に、個人事業主が従業員を雇用する際に必要な社会保険関連の手続きと流れを分かりやすくまとめました。
1.加入手続きを行う場所
加入手続きは、企業の所在地を管轄する年金事務所やハローワークで行います。
健康保険や厚生年金保険の手続きは年金事務所で、雇用保険の手続きはハローワークで実施します。
どちらの機関も地域ごとに管轄が分かれているため、事前に確認が必要です。
電子申請を利用することで、オンラインでの手続きも可能ですので、忙しい個人事業主の方にもおすすめです。
2.必要な書類
【健康保険・厚生年金保険の手続き】
新規適用届:会社設立後、初めて社会保険に加入する場合に必要な書類。
被保険者資格取得届:従業員が入社した際に、従業員を社会保険に加入させるための書類。
健康保険被扶養者(異動)届:従業員に扶養家族がいる場合に提出する書類。
給与台帳:従業員の給与額が確認できる書類で、報酬月額算定のために必要です。
【雇用保険の手続き】
雇用保険適用事業所設置届:初めて雇用保険の適用を受ける事業所として手続きする場合に必要。
雇用保険被保険者資格取得届:従業員が雇用保険に加入するための書類。
3.手続きの流れ
企業が設立されたときや、
新たに社会保険適用事業所となった場合、
「新規適用届」を年金事務所に提出します。
その後、従業員が入社するたびに「被保険者資格取得届」を提出します。
【健康保険・厚生年金】
入社日から5日以内に年金事務所へ「被保険者資格取得届」を提出します。
従業員に扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」も併せて提出します。
【雇用保険】
入社日から10日以内に「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出します。
提出後、健康保険証や雇用保険被保険者証が交付されるため、従業員に渡します。
4.電子申請の活用
「e-Gov」や「GビズID」などを利用して、健康保険・厚生年金・雇用保険の手続きをオンラインで行うことができます。書類提出の手間を省き、業務を効率化できます。
5.毎年の更新手続き(定期手続き)
【社会保険の算定基礎届】
毎年7月に提出する必要があり、従業員の4月から6月の給与額をもとに保険料の基準を算定します。
【労働保険年度更新】
労災保険・雇用保険に関する保険料を毎年見直し、7月10日までに手続きを行います。
社会保険の手続きは、期限が決められているため、速やかに正確に行うことが求められます。
また、電子申請の利用で手続き負担を軽減することも可能です。
任意適用のメリットとデメリット
任意適用の制度を利用することで、個人事業主でも従業員の厚生年金や健康保険に加入することが可能です。
メリットとしては、従業員は厚生年金保険に加入することで、将来的な年金受給額が増加し、医療の保障も充実します。
さらに、家族の扶養に入れることができるため、生活の安定にも寄与します。
しかし、デメリットとしては、社会保険料を事業主が従業員と折半で支払う義務が生じる点が挙げられます。
このため、経費が増えることになるので、経営計画に影響を与える場合があります。
任意適用を選択する際は、コスト面を十分に考慮し、慎重に判断する必要があります。
7
個人事業主の社会保険に関する注意点
個人事業主として社会保険に加入する際には、いくつかの注意点が存在します。
特に、加入義務や手続きの詳細について把握することで、後々のトラブルを避けることにつながります。
また、社会保険は従業員とその家族を守る重要な制度であるため、正しく理解しておくことが大切です。
任意加入や特定の業種に関するルールについても注意を払うことで、全体的な保障を整えることが可能となります。
個人事業主自身の社会保険加入
個人事業主自身の社会保険加入は、国民健康保険や国民年金が基本です。
ただし、従業員が5人以上の場合は、厚生年金や健康保険への加入も可能で、従業員の福利厚生にも影響を与えます。
事業主自身が厚生年金に加入する際には、年金の受給額が増える可能性があり、将来的に安心感を持つことができます。
それに加えて、加入手続きについても証明書類の準備や申請が必要ですので、効率よく進めることが求められます。
加入を検討する際には、保険料の負担や保障内容をしっかりと確認することが重要です。
従業員5人以下を雇う場合の留意点
従業員が5人以下の個人事業主は、社会保険への加入が任意となりますが、加入によるメリットも多くあります。
加えて、任意での加入に際しては、従業員の過半数からの同意が必要です。
このため、意思疎通が不可欠です。
従業員と話し合いを重ね、加入の意義や保険の内容について情報提供を行うことが、円滑な手続きのために大切です。
また、加入することで、特に医療面での保障が充実するため、従業員の定着率向上にも寄与します。
経営において、社会保険に関する判断は、長期的な視点が必要となります。
特定業種における社会保険の任意加入
特定業種に属する個人事業主は、社会保険の任意加入が認められています。
例えば、士業や農業、サービス業などの職種では、従業員数が少ない場合でも加入を選択することができます。
しかし、任意加入を決定する際には、コスト面と保障内容について考慮することが重要です。
特に、保障が不十分な場合でも、加入によるメリットが出るケースがありますので、十分な情報を基に判断することが求められます。
間違った選択を避け、経営を安定させるためにも、業種に特有の条件や法律について事前に確認することをお勧めします。
8
まとめ
個人事業主が従業員を雇用する際、社会保険の加入についての理解は不可欠です。
従業員数や業種によって異なる加入義務や任意加入の選択肢があり、それぞれの状況に応じて適切な判断をする必要があります。
社会保険は従業員やその家族を守るための制度であり、充実した保障を提供することが重要です。
また、個人事業主自身の保障についても考慮し、長期的な視点で制度を活用することが推奨されます。
任意加入のメリットやデメリットを理解した上で、従業員が安心して働ける環境を整えることが、事業の成長にもつながるでしょう。
これらの要点を意識し、適切な手続きを行うことで、より良い経営が実現できるはずです。
オススメの商材・サービスを集めてみました!
-

【超高額インセンティブ】光回線の販売パートナー募集
-

代理店 報酬増額中!!ソフトバンク法人携帯
-

顧客満足度No.1 / 浄水サーバー
-

【公式】キャリアから直接募集!販売パートナー
-

【不動産管理会社様向け】 ライフライン紹介高額報酬
-

選ばれる海洋深層水サーバー「エフィールウォーター」
-

【不動産・工務店様向け】太陽光、オール電化、蓄電池
-

外国人材ビジネス【高収入×社会貢献】
-

超高額インセンティブ!個人法人通信ライフライン商材
-
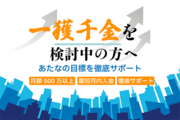
営業代理店募集 『ホームページ制作パッケージ』
-

【月商200万円可】PC1台とスキマ時間で新規事業
-

日本初上陸「フードデリバリーサービ」開拓営業募集
まずは資料請求してみませんか?もちろん無料です。
(簡単な会員登録が必要です)
資料請求してみる





 0120-536-015
0120-536-015